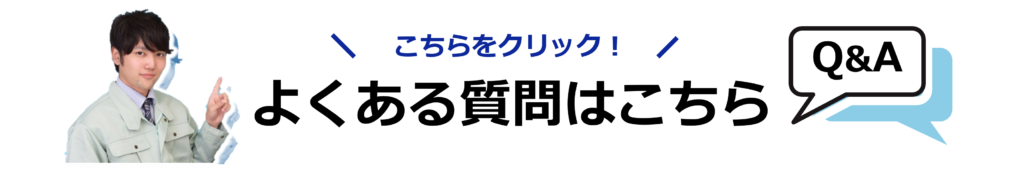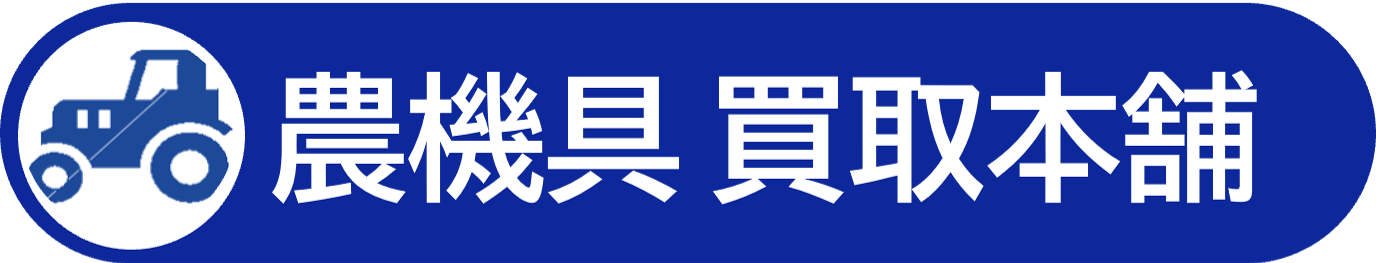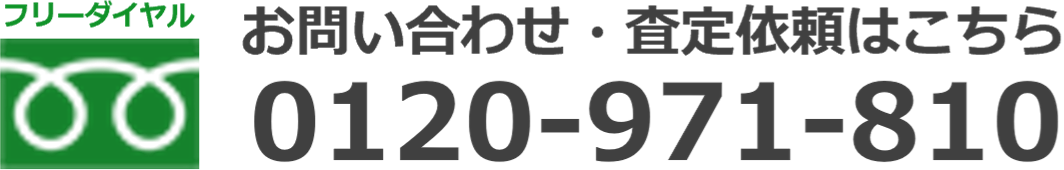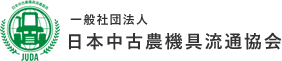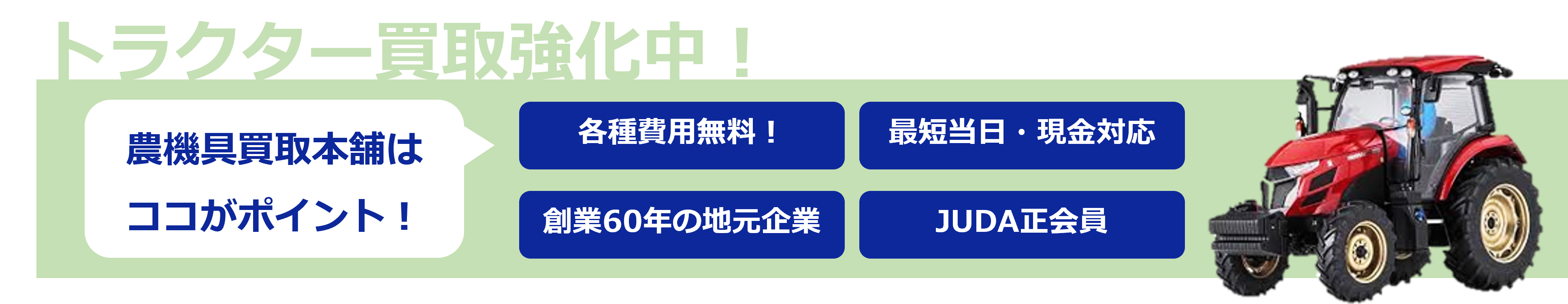

離農問題への対策が求められています。これは、高い離農率が農業の担い手不足や地域社会に影響を与えているからです。総務省が全国18都道府県に調査をしたところ、2014年度に農業の雇用事業による研修を受けた1,591人のうち、35.4%に当たる564人が離農していました。本記事では、離農の原因と対策について考察します。
関連記事:離農とは?離農の問題点や方法(農地転用・農機具の処分・給付金手続き)を解説
目次
離農の背景と原因とは?
離農の背景と原因を理解することが対策の第一歩です。原因を把握することで、効果的な対策を立案できます。日本国内の離農の状況では、高齢化や都市への人口流出が離農の原因の一部であることがわかります。また、新規就農者の高い離農率の理由として、仕事と現場業務のミスマッチや、キャリア支援体制の不備が要因となっていることが報告されています。
1. 高齢化
高齢化は、農業従事者の減少や後継者不足を引き起こしています。統計局の調査によれば、日本の農業従事者の平均年齢は67歳と高く、若手農家の不足が深刻化しています。また、農業従事者全体の約64%が65歳以上であり、今後さらなる担い手不足が懸念されます。
2. 都市への人口流出
都市への人口流出も、離農の原因の一つです。経済的な機会を求める若者が地方から都市へ移住することで、農村地域の人口が減少し、農業の担い手が不足しています。また、農村地域の過疎化が進むことで、地域コミュニティの維持が困難になり、農業の持続が厳しくなっています。
3. 仕事と現場業務のミスマッチ
新規就農者の離農率が高い一因として、仕事と現場業務のミスマッチが挙げられます。新規就農者が農業に対する理想と実際の業務内容にギャップを感じることがあります。例えば、農業は季節性が強く、長時間労働が必要なことや、収益性が低いことが挙げられます。これらの理由から、新規就農者が離農を決断することがあります。
4. キャリア支援体制の不備
新規就農者のキャリア支援体制の不備も、離農率が高い原因となっています。農業への就業を支援する制度やプログラムが不十分であるため、新規就農者が農業を継続する意欲を持ち続けることが難しくなります。また、農業技術の習得や経営ノウハウの継承が十分に行われていないことも、新規就農者の離農につながっています。
農業従事者の減少が地域経済に与える影響も大きい
農業従事者の減少は、日本の地域経済に深刻な影響を及ぼしています。以下にその主な影響をまとめます。
地域経済の縮小
農業は多くの地方経済において基盤となる産業であり、農業従事者の減少は直接的に地域経済の縮小を引き起こします。農業が衰退すると、農産物の生産量が減少し、それに伴い農業関連の雇用機会も減少します。これにより、地域の経済活動が低下し、商業やサービス業にも悪影響を及ぼすことになります。
食料自給率の低下
農業従事者の減少は、食料自給率の低下にもつながります。日本は食料自給率が低く、農業の衰退は国内の食料供給に対する依存度を高め、外部からの供給に依存するリスクを増大させます。これにより、食料安全保障の観点からも懸念が生じます。
地域文化の衰退
農業は地域の文化や伝統と深く結びついています。農業従事者の減少により、伝統的な農法や地域特有の文化が失われる危険性があります。これにより、地域のアイデンティティが弱体化し、観光資源としての価値も低下する可能性があります。
人口流出の加速
農業従事者の減少は、地域の人口流出を加速させる要因ともなります。若者が農業に魅力を感じず、都市部へ移住することで、地方の人口がさらに減少し、地域経済の活力が失われるという悪循環が生じます。
地域社会の活力喪失
農業の衰退は、地域社会の活力をも奪います。農業が基盤となっている地域では、農業の衰退が商業の空洞化や地域のサービスの低下を招き、結果として地域全体の活力が失われることになります。
これらの影響は相互に関連しており、農業従事者の減少がもたらす地域経済への影響は、単なる経済的な問題にとどまらず、社会的、文化的な側面にも広がっています。したがって、農業の持続可能性を確保するためには、地域全体での取り組みが必要です。
農業従事者の減少を防ぐためにどのような政策が必要か?
農業従事者の減少を防ぐためには、以下のような政策が必要です。
1. 就労環境の改善
農業の労働条件を改善することは、新規就農者の定着を促進するために不可欠です。具体的には以下の施策が考えられます。
- 労働時間の短縮と合理化: 労働時間を明確にし、過酷な労働環境を改善するための取り組みが必要です。これには、作業効率化のためのITツールの導入や、休暇制度の見直しが含まれます。
- 賃金の適正化: 農業従事者が安定した収入を得られるよう、最低賃金以上の賃金を確保し、安定的な契約形態を提供することが重要です。
- 職場環境の整備: トイレや休憩所の衛生環境を改善し、温熱環境の対策を講じることで、働きやすい環境を整える必要があります。
2. 外国人技能実習生の受け入れ
農業分野での人手不足を解消するために、外国人技能実習生の受け入れを積極的に進めることが重要です。これにより、労働力を補充するだけでなく、技術やノウハウの伝達も期待できます。ただし、言語や文化の壁を乗り越えるためのサポート体制を整えることが必要です。
3. IT化とスマート農業の推進
IT技術を活用したスマート農業の導入は、農業の効率化や省力化を図る上で重要です。具体的には、以下のような技術が考えられます。
- 精密農業: GPSやドローンを用いた農作業の効率化を図ることで、労働力に依存せずに高品質な農産物を安定して生産することが可能になります。
- 自動化技術の導入: ロボットや自動運転トラクターの導入により、重労働を軽減し、労働力不足を補うことができます。
4. 農地の集約と大規模化
農業経営の効率を向上させるために、農地の集約や大規模化を進めることが必要です。これにより、大型機械の導入が可能になり、作業効率が向上します。また、法人化を進めることで、経営の安定性や資金調達の容易さが増すことも期待されます。
5. 新規就農者への支援
新規就農者が定着するためには、以下のような支援が必要です。
- 研修制度の充実: 農業技術や経営に関する研修を充実させ、新規就農者が必要なスキルを身につけられるようにすることが重要です。
- 資金援助や融資制度の整備: 新規就農者が初期投資を行いやすくするために、無利子融資や補助金制度を整備することが求められます。
これらの政策を総合的に実施することで、農業従事者の減少を防ぎ、持続可能な農業経営を実現することが可能になります。地域全体での支援やコミュニティづくりも重要な要素です。
まとめ
離農の原因と対策について詳細に説明しました。高齢化や都市への人口流出などの背景を踏まえ、新規就農者の支援や育成、農業の持続可能性を高める取り組みなど、効果的な対策を立案することが求められます。本記事が、離農問題に取り組む方々にとって有益な情報となることを願っています。
とりあえず無料で査定額を確認してみませんか?
そのあとはスタッフからの質問にお答えいただければ大丈夫です。